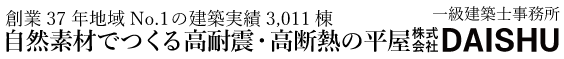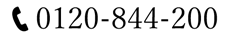『平屋の換気計画をどう考える?』
こんにちは。平屋専門建築士の長沢です。
換気は、健康的で快適な住環境を保つために不可欠です。
平屋の特性に合わせた換気計画を立てることで、空気の循環を良くし、湿気や匂い、カビなどの問題を防ぐことができます。
2003年の建築基準法改正以降、すべての建築物の居室に対して建材や換気設備の規制がかけられるようになりました。
これは住宅の高気密化と化学物質を使用した建材の使用によりシックハウス症候群を引き起こすなど、健康への影響を懸念しての事でした。
これ以降建設される住宅には換気設備の設置が義務付けられ、いわゆる24時間換気システムの設置が必要になりました。
従来の日本の木造家屋であれば低気密ですき間が多いうえ、天然の木材を使用している為、健康への影響は懸念される問題ではありませんでしたが、
近年の住宅において換気計画は重要となります。
単に換気と言っても自然換気と機械換気がありますので、今回は平屋ならではの換気計画をご紹介します。
まず、自然換気です。平屋における換気の特性としてワンフロアである為、空気が横方向に流れやすく、窓の配置が重要となります。
これは単に建物内だけで計画するのではなく、隣隣地や道路など周辺からの風の流れを考慮した窓の配置をします。
建物内部の計画では対角線上に窓を配置することで横方向の空気の抜けがよくなります。
また、平屋では屋根からの太陽光の熱をダイレクトに居室に伝えやすく、地面からの照り返しがある為、二階建て住宅と比べて熱くなりやすいといわれます。
対策としては勾配天井+高窓をうまく使うことで暖かい空気が上に抜けやすくなり、さらなる換気効果が見込まれます。
-1024x683-1-350x233.jpg)
※写真はイメージです。
次に機械換気です。24時間換気システムとは、2003年の建築基準法改正以降、化学物質(ホルムアルデヒド等)を発散する建材を使用しない場合でも、機械を用いて居室の空気を外気と入れ替えることで、居室内の空気を新鮮に保つ役割を果たしてくれるシステムの事です。
例えば住宅の場合は1時間あたりに部屋の空気の半分以上が入れ替わることが基準となっています。
これは住居全体の空気を入れ替えるものなので、キッチンやトイレのような局所的な換気とは別のシステムです。これらの換気の方法は用途やシーンによって3種類に分けられそれぞれの特徴があります。
1.第一種換気
給気と換気の両方を機械により強制的に行うものです。機械により給気・換気できる量が決まっている為、確実に空気を入れ替えることができ、3つの中で最も安定して換気をすることができます。
ただし、給気・換気どちらも機械である為、ダクトやファンなど設備の費用がかかり導入費用が高くなります。主に近年の高気密住宅やオフィスで使用されています。
2.第三種換気
給気は自然に任せ、換気を機械により行うものです。キッチンやトイレなどの湿気やにおいを、他のエリアに広がる前に排出したい場所において採用されている最も一般的な換気方法です。
換気のみを機械を使用するため、導入費用を抑えることができ、消費する電力も第一種換気に比べて抑えることができます。
3.第二種換気
給気を機械で行い、排気は自然に任せるものです。機械的に空気を取り込むことで屋外より室内の方が気圧が高くなる為、外部からチリやほこりの侵入を防ぐことができ、室内を清潔に保つことができます。
そのため住宅での使用は一般的ではなく、手術室や工場のクリーンルームなどに使用されます。
このように3つの換気方法がありますが、住宅において一般的なのは1.第一種換気と2.第三種換気ということになります。
どちらを選択するかはそれぞれメリットデメリットを把握した上でご予算や目的、こだわりなどによって選ぶことが出来ます。
今回は平屋ならではの自然換気の計画と機械換気の方法をご紹介しましたが、平屋の換気システムを計画する際は、窓の配置、換気システムの選択、各部屋の換気経路をしっかり考慮することが重要です。
また、自然換気と機械換気を併用することで効率的に空気を循環させ、快適な住環境を実現できます。
千葉市、印西市、八千代市、市川市、船橋市近郊で平屋住宅を建てるなら是非DAISHUにご相談ください。
風通しがよく、健康快適な住まいづくりをご提案させて頂きます。
◆自然換気を考えたパッシブデザインについて知りたい方はこちら◆
→「平屋住宅におけるパッシブデザインとは?」

二級建築士
宅地建物取引士